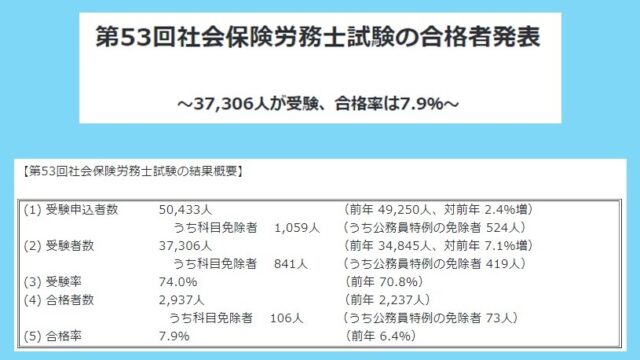シフトが減っている高齢パートさんに対して事業主が注意すべきこと

ひと昔前までは、「65歳で完全リタイアし、その後は年金で生活する」という考え方が主流でした。しかし、現在ではこの前提が大きく変わってきています。
その背景には、日本の生産年齢人口の減少に伴う労働力不足や、年金水準の相対的な低下があると個人的には感じており、こうした就労の広がりを必ずしもポジティブな現象として受け止めることはできません。
 65歳以上の就労者(被用者)の多くは、パート従業員として働いています。若い頃はフルタイムに近い勤務形態だった方も、年齢を重ねることで体力の衰えを感じ、自ら申し出てシフト(出勤日数)を減らすケースが最近私の顧問先様でも多く見受けられます。
65歳以上の就労者(被用者)の多くは、パート従業員として働いています。若い頃はフルタイムに近い勤務形態だった方も、年齢を重ねることで体力の衰えを感じ、自ら申し出てシフト(出勤日数)を減らすケースが最近私の顧問先様でも多く見受けられます。
こうした方々にとって、特に注意すべき点の一つが「就業日数」です。
ここで言う「就業日数」とは、正確には「賃金支払基礎日数」のことを指します。この日数には、有給休暇など、事業主が賃金を支払う対象となる休暇も含まれます。
この「賃金支払基礎日数」は、失業手当(65歳以上の場合は「高年齢求職者給付金」)の受給資格を判断するうえで、極めて重要なデータとなります。(ここでは雇用保険の内容に絞って説明します)
「高年齢求職者給付金」の受給要件の一つとして、「離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で6ヶ月以上あること」が定められています。
そして、この「被保険者期間」として認められるためには、対象期間(通常1ヶ月)において「賃金支払基礎日数」が原則11日以上、もしくは就労時間が80時間以上である必要があります。
そのため、シフトを減らした結果、「賃金支払基礎日数」が10日以下の月が続いた場合、当該期間が「被保険者期間」としてカウントされず、離職後に「高年齢求職者給付金」の受給対象外となるケースも想定されます。これは、長年雇用保険料を支払ってきた方であっても例外ではありません。
こうした不利益を避けるために、雇用主が取るべき対応としては、以下の2点が挙げられます。
① 雇用保険の被保険者に対しては、「月の賃金支払基礎日数」が10日以下とならないよう、勤務日数を調整すること。
② 上記の対応が継続的に困難と見込まれる場合は、労働条件を変更し(雇用契約書の再締結を推奨)、雇用保険の被保険者資格を喪失させる手続きを行うこと。

なお、雇用保険の被保険者資格には「週の所定労働時間が20時間以上」という要件もあるため、労働時間の減少によりこの要件を満たさなくなる可能性も考慮する必要があります。
但し、雇用保険の被保険者資格の条件を満たさなくなってもわざわざハローワークから個別の企業に連絡をしてくることは決してありません・・・
※「マルチジョブホルダー制度」と言う複数の事業所で働く65歳以上の労働者が雇用保険に加入できる特例制度もありますが、その詳細については割愛します。
以上、少しでも参考になれば幸いです。