退職代行サービス業者からの連絡は冷静に対応を
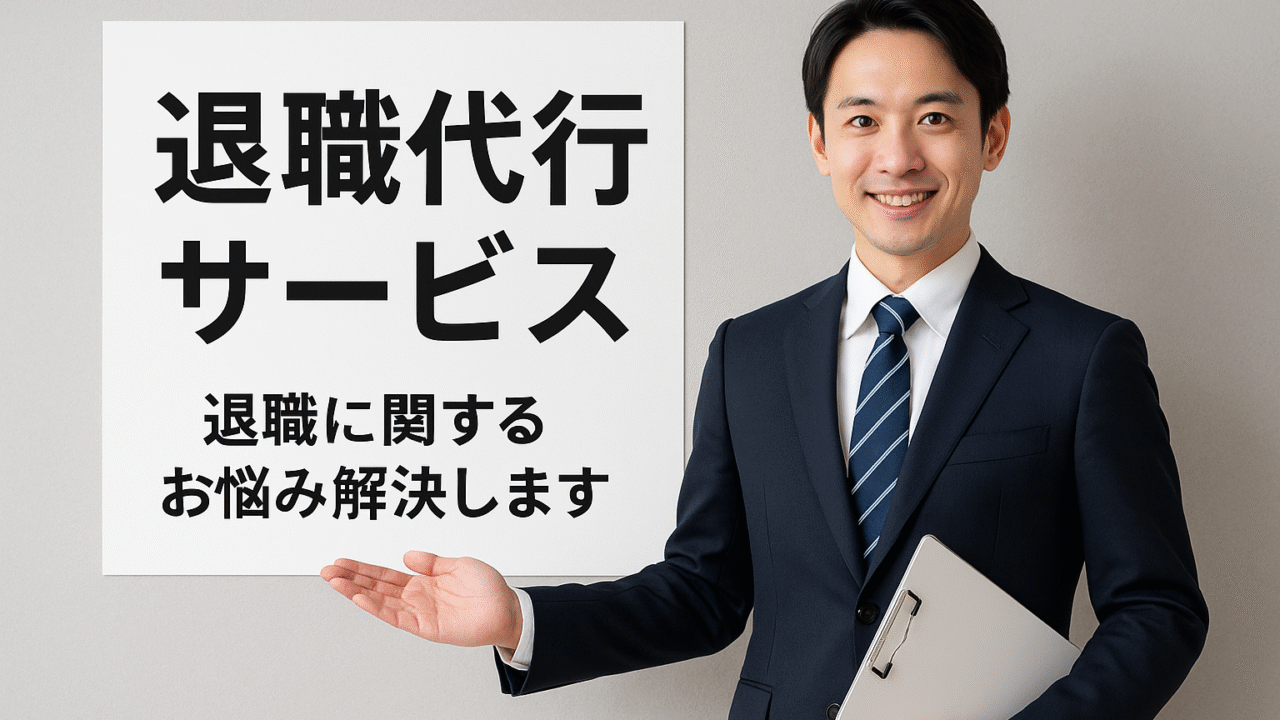
近年、企業が退職代行業者から従業員の退職意向を突然伝えられるケースは珍しくなくなりました。
「退職の意思くらいは本人が直接上司に伝えるべきだ」という、いわば“昭和的価値観”を持つ私にとっては理解しがたい面も正直ありますが、これも時代の流れと受け止め、企業側も冷静に対応する必要があります。
まず、退職代行業者から従業員の退職に関する連絡が入った場合、感情的にならず、その業者が弁護士か労働組合か、それ以外の民間業者かを確認することが重要です。
♦弁護士の場合
弁護士は代理権を有し、本人に代わって全ての法律行為を行えます。したがって、原則として弁護士を通じて退職手続きを進めることになり、企業側がその方法を拒むことはできません。
♦労働組合の場合
本人がその労働組合の組合員であれば、労働組合には団体交渉権があるため、企業側は交渉窓口として組合に対応する必要があります。
♦上記以外の民間退職代行業者の場合
行えるのは「退職の意思を会社に伝えること」に限られ、法的には“代理”ではなく“使者”です。つまり、退職届の提出や意思の伝達が範囲内であり、退職日や条件の交渉、未払い残業代の請求などは違法行為(非弁行為)とみなされる可能性が高くなります。もし“使者”の範囲を超える要求があれば、違法性を指摘し拒否する対応が基本です。
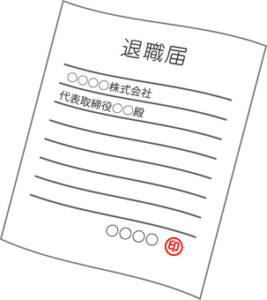
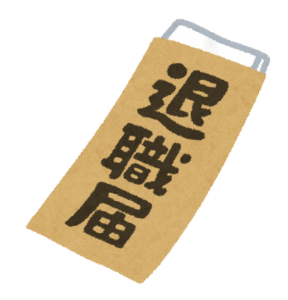
もっとも、“使者”を通じた退職意思表示も法的には有効とされ、本人の退職意思そのものを否定することはできません。特に期間の定めのない雇用契約では、民法627条1項により「申し出から2週間」で雇用契約は終了し、企業側がこれに抗することは極めて困難です。
突然、退職代行業者経由で退職意思を伝えられれば、多くの企業は戸惑います。特に信頼していた従業員であればなおさらです。私の経験上、むしろ信頼の厚い従業員ほど退職代行を利用することが多く、これは「信頼関係があるからこそ、自ら退職を切り出しにくい」という心理によるものではないかと考えます。特に若年層にこの傾向が見られます。
退職代行業者を通じた退職には否定的な感情が伴いやすいものの、これも時代の変化の一つです。企業としては感情的にならず、法的な位置づけを踏まえて粛々と対応していく姿勢が求められます。







